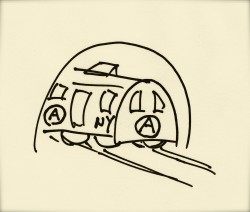181丁目地下鉄のエレベーターマン (その1)
- 2013.01.03
- その他
(約束通りドキュストーリーの第一弾です。)
「181丁目地下鉄のエレベーターマン」
ニューヨークの地下鉄を僕は大好きだ。
といってもただ好きというだけではなく、なにか怖いと好きが混じった複雑な感じ。
いろんな人種が普通に混じりあって大きな音を立てて走る地下鉄を毎日使って、僕は生活していたわけです。
決して安心してしまってはいけない、どこか不気味な危険なところがあるのに、同時にとても人間的なところがあるのが、僕を好きにさせてしまうのです。
マンハッタン島の西、これ以上は北にはいけないというと所に、ワシントンハイツと呼ばれる地域があります。
マンハッタンの中でも特に経済的にも、人種的にも、文化的にも、混合している所。英語の表示もあんまり無いドミニカンやプエルトリカンのラティーノの住む地区、すぐ南はハーレムで、黒人の住む地区。ユダヤ人の住む地区。裕福な白人の住むハドソン河の地区など、小さく地区は別れていても、そこはニューヨーク。普通にいろんな人が混じって生きています。
ここの真ん中にあるのが、181丁目の地下鉄の駅。
ワシントンハイツというくらいで、ここはマンハッタンでもっとも標高が高い所らしい。
駅のホームには殆どの人がエレベーターを使います。建物にすると12階くらいの深さのあるエレベーター。
どす黒くなってしまったステンレスで囲まれた8フィート四方のエレベーターの箱は、不気味な重苦しさがある。
人が沢山乗っていると呼吸をしてはいけないような窮屈さが、そして人が乗っていないとこれはこれで、怖くなってしまうような空間。
僕が作ったキューバを舞台にしたドキュメンタリー映画のエディターで親友のメリッサが、この地域に住んでいるので僕は時々、このエレベーターを使うわけです。
そしてその度に呼吸を止めながら、暖かい涙を感じるのです。
***
***
今では無人になっているけれど、10年前までは、一人のエレベーターマンが運転をしていた。
身体のとても大きな、眼も大きくてクリクリした、唇の厚い年配の黒人の男。
ちょっと茂れてでも潤いのある声だった。Rに強い訛があって、どこか南の海を感じさせてくれる爽やかさがあった。
いつも汗をかいているのに、決して体臭は感じさせなかった。
(明日に続く:と言っても読んでくれるかなあ。)